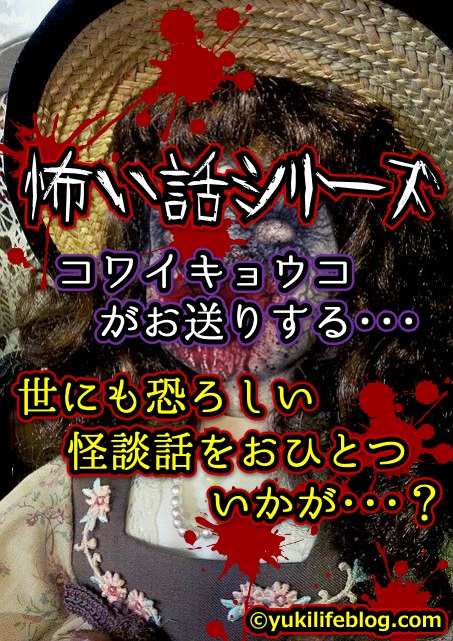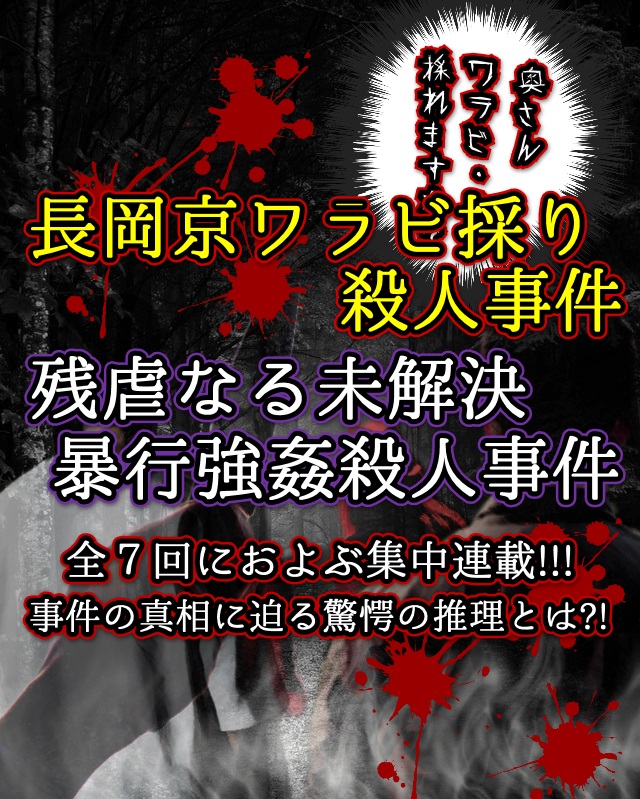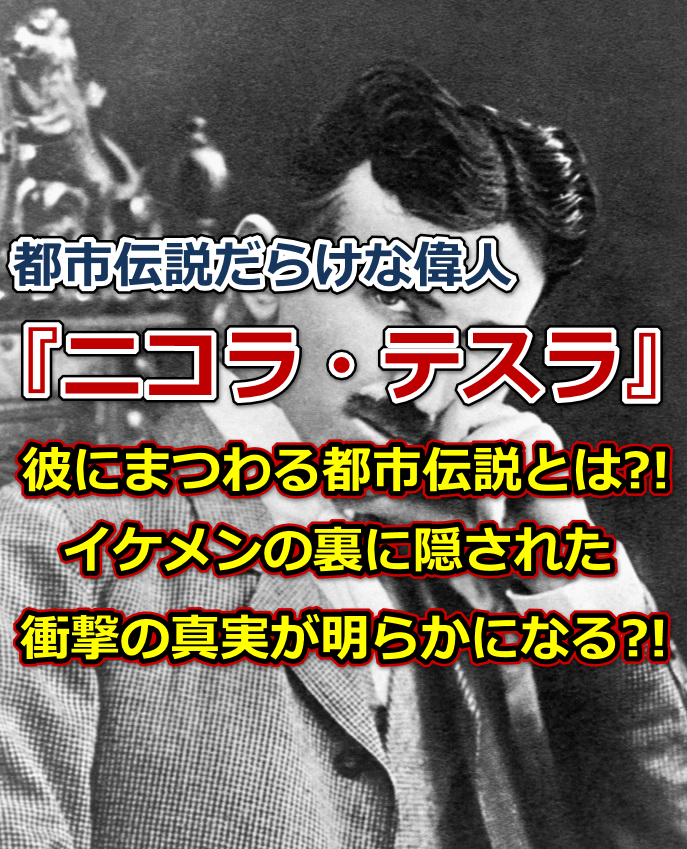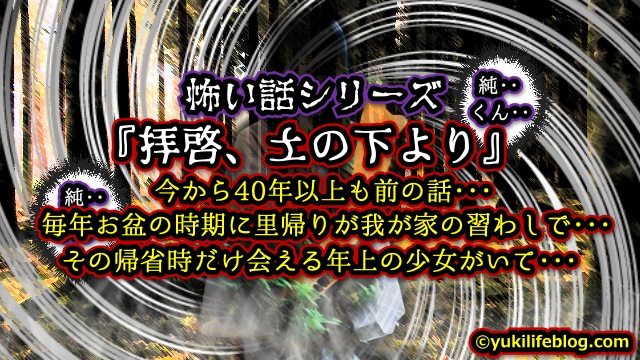とある悲しい少女にまつわる怖ろしい話・・・
『拝啓、土の下より』
今から40年以上も前の話・・・
毎年お盆の時期に里帰りが我が家の習わし・・・
その帰省時だけ会える年上の少女がいて・・・
今回は怖ろしい怪談話『拝啓、土の下より』をお伝えします。

毎度おなじみ心霊界の石原さとみこと、コワイキョウコです・・・
今回は怖くはあるけど、ちょっぴり悲しく切ないお話・・・
お姉ちゃんはきっと・・・
助けて欲しかったんでしょうけど・・・
ラストの2行で垣間見える少年の感情・・・
どう言う意味なのか・・・
怖い・・・(汗)
それでは怖い怖い怪談話・・・
『拝啓、土の下より』
どうぞお楽しみください・・・
※このお話は4分ほどで読むことができます。
『拝啓、土の下より』怖い話シリーズ134

今から40年以上も前の話だ。
その夏、私は家族と田舎に住む祖父母の家を訪れていた。
毎年お盆の時期になると、里帰りをするのが我が家の習わしだった。
当時小学2年だった私は、年に一度のこの里帰りを楽しみにしていた。
田舎には普段一緒に遊んでいる友達たちもいないし、遊園地やおもちゃ屋もない。
代わりに都会にはない、豊富な自然があった。
幼い私にとって、それは最高に面白い遊び場であった。
祖父母の家の周りに広がる、夜になると蛍が飛び回る一面の水田。
小魚を捕まえたり、水遊びをすることができる清流。
子供の大好きなカブトやクワガタがわんさと採れる深い森。
毎年、私はそれこそ一日中、外を遊び回っていた。
そして何より、年に一度だけ会うことのできる友達がいた。
近所に住むふたつ年上の女の子で、私は「お姉ちゃん」と呼んで慕っていた。
彼女と一緒に遊ぶことが、田舎に行く一番の楽しみだった。
しかし・・・、この夏私はひとりだった。
田舎に着いた初日、荷物を祖父母の家に置くや否や、私はお姉ちゃんの家に向かって駆け出していた。
今にしてみれば、祖父母は私を止めようとしていたのだが、その制止も私の逸(はや)る心には届いていなかった。
息を切らしてお姉ちゃんの家の前まで来ると、ワクワクしながら呼び鈴を鳴らした。
しばらく待つと、お姉ちゃんの母親が顔を覗かせた。
一年前に見たときにはふくよかな印象の女性だったが、その時の彼女はまるで空気が抜けた風船のようにげっそりと痩せており、目には生気がなかった。
「ああ――……、純くん、今年も来たのね……」
「うん!おばちゃん、お姉ちゃんは?」
私は弱弱しい彼女の様子に気をかけるでもなく、目当ての人の在否を問うた。
「うん――、」
一瞬口ごもる。そして、私から視線を逸らすかのようにうつむいた。
「ごめんね、今はいないの。友達とお泊りに行っちゃって……。今年は純くんと一緒に遊べないと思うわ……」
それだけ言うと、おばちゃんは静かに家の中に戻っていった。
私はすっかりしょげて、祖父母の家に戻ってきた。
先ほどの話を聞かせると、祖父は少しの間黙った。
「そうか……。うん、爺ちゃんもお姉ちゃんはいないって聞いてたんだ。だからさっきお前を止めようとしていたんだよ。残念だが、我慢してな」
祖父は優しく私の頭を撫でた。
『ほら純くん、蛍だよ。都会にはこんなのいないでしょ?』
『純くん、早くおいでよ。水が冷たくて気持ちいいよ。あ、魚いるよ!』
『純くん――』
夜になると蛍が飛び回る水田も、小魚を捕まえたり、水遊びをすることができる清流も、今年はお姉ちゃんがいないというだけで、すべてが色あせてしまったかのようだった。
――カナカナカナカナカナ……
私は翌日、一番最初に鳴いたヒグラシの鳴声を合図に夜明け前に目を覚ました。
普段学校のある時には、母親に布団をはがされるまで起きない私だったが、田舎に来ている時だけは自然と目を覚ますことができた。
家族は皆まだ寝静まっている。
物音を立てないように着替えを済ませ、補虫網と虫かごを持って家を抜け出した。
昨年までだったら、玄関の戸を開けるとお姉ちゃんが待ってくれていた。
そしてふたりして手をつなぎ、私たちが「秘密のクヌギ」と呼んでいた、カブトやらクワガタやらがよく集まる木のある森まで歩いていったのだった。
彼は誰時(かわたれどき)というのだろうか。
私はその時間が一番好きだった。
薄暗く、人の顔もぼんやりとしてわからない時間帯。
その薄闇の中、ぼんやりと浮かび上がるお姉ちゃんの白いワンピース。
夏の長く充実した一日が始まる前の刹那の時間。
大好きなお姉ちゃんと二人きりで過ごす内緒の時間。
私にとって、それは特別な時間だったのだ。
今年は残念ながら一人で森へと向かう。
森の入り口へと着くと、ヒグラシの鳴声がまるで夕立のように頭上の木々から降ってきていた。
繁みをかき分け、細い獣道を進む。
迷うことはない。
――カナカナカナカナ……
――カナカナカナ……
――カナカナカナカナ……
ヒグラシの輪唱と、ハッハッハッという自分の吐息だけが鼓膜を刺激する。
網膜には薄暗く、曖昧模糊とした雑木林だけが映る。
夢の中にいるようだった。
不意に、私の目になにか白いものが映った。
木々の間をヒラヒラと、漂うように移動する。
――なんだろう。
こんな時間にこんな場所で、誰かがいるなんて思えない。
けれどもそれは私の進行方向に、見えつ隠れつヒラヒラと。
私はそれを追いかけた。
怖いとも思った。
薄気味悪いとも思った。
しかし夢の中のようなこの夜明け前の森が、私の心のどこかを麻痺させていたように思う。
――ガサガサ、
――ヒラヒラ
――ハッハッハッ、
――ヒラヒラヒラ
不意に目の前が開けた。
そこは目指していた「秘密のクヌギ」の場所だった。
大人の胴回りほどの太さの幹の、ちょうど私の背丈ほどの位置から樹液が溢れ、カブトやらクワガタやらカナブンやら蝶々やら、子供にとって宝石のような昆虫たちがジュクジュク、ピチョピチョそれをすすっていた。
しかし私はその宝島のようなクヌギより、その木の手前に立っているものに目を奪われていた。
それはすっと静かに立っている。
暗い森、黒い地面、その中に・・・
白い、
白い白い白い。
腕が一本生えていた。
その先は真っすぐに天を目指して。
その足元は、黒い湿った腐葉土の中から。
「お姉ちゃん――?」
私がなぜそう思ったのかは、私自身にもわからない。
ただその白く細い手のように見えるものが、彼女のものだと直感的に思っていた。
私はそれに近づいた。
花の匂いに釣られる虫のようにふらふらと。
果たして、それは腕ではなかった。
少女の腕のように見えたもの・・・
それは、白くて細い、すべすべした茸(キノコ)であった。
私はその場にひざを着いた。
そして、その茸の足元を静かに手で堀っていった。
――ざっざっざっざっ
――カナカナカナカナ……
――ジュクジュク、
――ピチャピチャ
地面の土は柔らかく、子供の手でも簡単に掘り進められた。
一掻きごとに冷たい土の中から、木の葉と虫と微生物の腐った良い匂いが漂った。
茸の根は地面の中で一層白く、底へと伸びていた。
それでもそれほど深くはないところで、私の手は茸の根にたどり着いた。
そしてそこには・・・
『純くん――』
お姉ちゃんがいた。
その後、家に戻ってこのことを家族に告げると、小さな田舎町は騒然となった。
ただちに警察が森へと向かい、秘密のクヌギの前の地面の底から、お姉ちゃんの遺体を回収した。
おばちゃんは泣いていた。
私には知らされていなかったが、お姉ちゃんはその年の前年の冬、行方不明になっていたそうだ。
誘拐の疑いもあるということで、捜査も行われていた。
しかし一向に見つからなかった。
私は何度も警察に事情を聞かれた。
小学2年の男子に容疑は向かなかったが、なぜあんな時間、あんな場所にいたのか、なぜ地面を掘り返す気になったのか、と再三問われた。
私は虫取りのこと、茸のことを正直に話し、大人たちも納得せざるを得なかった。
長じてから植物に興味を持った私が、ある書物を読んでいて知ったことだ。
「冬虫夏草」という植物がある。
読み方はそのまま、トウチュウカソウだ。
写真などを見ると、ひょろりとした細長い茸だが、その根元には蛾や蝉の幼虫が付いている。
冬虫夏草とは生きた蛾や蝉の幼虫に寄生する茸の一種だ。
幼虫から養分を吸い上げ死に至らしめ、子実態を結ぶ。
昔は、冬の間は虫の姿で過ごし、夏になると草になると信じられたことからこの名が付いたものらしい。
漢方の生薬や、薬膳料理の素材としても用いられる。
あの日、お姉ちゃんの亡骸から生えていたのは茸だった。
人の亡骸から生える茸が、本に載っていた冬虫夏草と同じものかどうかはわからないが、冬に何者かに誘拐され土の中に埋められたお姉ちゃんは、夏に茸となって私の前に現れた。
森の中で私が追いかけた白いものや、お姉ちゃんの遺体を掘り当てたときに聞いた『声』など、あの日のことにははっきりしないことが多すぎた。
しかし、私は度々あの森でのことを夢に見て、そしてその度にこう思うのだった。
――ああ、
――あの美しい茸をもう一度見てみたい。
『拝啓、土の下より』怖い話シリーズ134

↓↓↓ 次にオススメの記事 ↓↓↓